
みなは自分の心臓がドキッとするのを感じた。
大学時代お世話になり、密かに思いを寄せていた二つ上の先輩の鈴木さんだったのだ。
向こうは私の事を覚えているのだろうか。
覚えているはずもないか、友達の影になり話に混ざっていただけの私の事など。
そんな思いが浮かんだ。


美しい😊
 2025.12.17本日お休みでーす。
2025.12.17本日お休みでーす。 2025.12.16本日もありがとうございました。
2025.12.16本日もありがとうございました。 2025.12.16本日もよろしくお願い致します
2025.12.16本日もよろしくお願い致します 2025.12.15本日もよろしくお願いします
2025.12.15本日もよろしくお願いします 2025.12.12本誌も宜しくお願い致します
2025.12.12本誌も宜しくお願い致します 2025.12.11本日もよろしくお願いします
2025.12.11本日もよろしくお願いします 2025.12.10本日も宜しくお願い致します🥺
2025.12.10本日も宜しくお願い致します🥺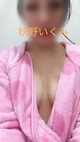 2025.12.08本日もよろしくお願い致します
2025.12.08本日もよろしくお願い致します 2025.12.06おはようございます。本日もよろしくお願い致します
2025.12.06おはようございます。本日もよろしくお願い致します 2025.12.04本日も宜しくお願いします
2025.12.04本日も宜しくお願いします
すてき!! たけ